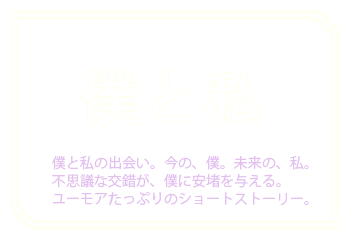僕が私に出会ったのは出張先のビジネスホテルだった。いつものシングルルーム。そして、いつもの芯に溜まった気だるさ。五十も半ばを過ぎると、なかなか簡単に疲労は抜けてくれないものだ。ただ、はっきり言って、今は全く違っている。そう、僕は私によって変わったのだ。まさに新しい自分。新たな人生。僕は私によって大いなる活力と勇気をもらったのだ。
僕はこのことについて、全ては話さない。いや、話すことができないのだ。ただ、ここでは簡潔に、極めて簡単に、私との出会いを語ってみたいと思う。もちろん、それを信じるか、また信じないかは、聞く側の都合で一向に構わない。それらはこの僕が気にすることではない。ただし、この話には虚構は一切含まれていない。このことだけは前置きをしておきたい。
あの夜。そう、ビジネスホテルでのあの夜。僕はいつものように、ユニットバスでシャワーを浴びていた。異変は洗髪の際に起こった。微かな物音。そして気配。明らかに僕のものとは違う指さばき。僕の指と、誰かの指先。もちろん目を開けてみる勇気などなかった。ただし、恐怖もなかった。それは実に不思議な感覚だった。しばらくの間、僕はされるがままでいた。
最初、僕はそれを疲労のせいにした。そうしないと、この事態を理解することはできなかったからだ。間もなく、異変は収まった。僕はバスタオルで身体をまとい、部屋に戻った。そして冷蔵庫からビールを取り出すと、素早く栓を開け、目を閉じたまま、中身を一気に喉へと流し込んだ。コクのある苦みが、喉元で程よく発散した。僕は目を開けた。そこに私がいた。
椅子に座ったひとりの老人。ロマンスグレーの紳士。僕を見る彼。彼を見る僕。そこで交錯する妙な親しみ。僕と彼。そして彼と僕。
「私は未来の君だ」
「未来の、この僕」
僕の頭の中は相当に混乱していた。今、僕は未来の僕を目の当たりにしている。そして彼は過去の僕を見つめている。未来の僕。過去の僕。現在の僕はここにいる。僕は、未来の僕と出会いながら、過去の僕としてここで生きている。
「特に問題はない」
「あなたは即ち僕」
未来の僕。僕は目の前にいる老人となる。しかもそれは、全ての活力を喪失した物体ではない。あらゆる光から見放され、死を待ち続ける姿でもない。生きとし生ける、れっきとした人間。柔和さと朴訥さ。真っ直ぐな目の奥の輝き。
僕はあえて未来に問うた。けれども私はそれを遮った。過去も問うた。私は首を横に振った。そして僕を誇りに思うとだけ言った。
僕は僕を誇ればいい。過去はもう十分に生きた。正しさも、過ちも、その時々で噛み締めた。それはそれで、もういい。そして、未来も、まだいい。未来は必ずやって来る。けれども、未来の為に生きるのではない。これまで通りに、その時々を生きるだけで、それだけでいい。過不足などはない。一切ない。生きるのだ。まだまだ生きるのだ。そう私は僕に告げた。
私は姿を消した。いつもの静けさが再びそこに戻った。疲労はすっかり身体から抜け、僕は深い眠りへと沈んだ。目が醒めた時、僕は自分を疑った。僕が見たのは、一体誰だったのか。現実か、それとも夢か。いや、明らかにそれは事実だった。僕は確かに私を見た。そして、私もまた僕を見ていた。こうして、僕は、私と出会った。同時に、私も、この僕と出会った。
以来、僕は変わった。いや、変えられたのだった。僕は僕を慈しむようになった。それは自己愛などではない。自分を愛せない人間に、一体誰を愛せるというのか。自分を大切に出来ない人間に、一体誰を大切に出来るというのか。失敗もいい。成功もいい。悲哀もいい。喜びもいい。過不足なく生きる。僕と私。私と僕。兎にも角にも、生きることで十分いいのだ。
.